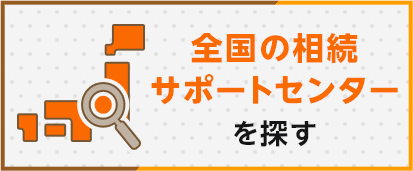所有者不明土地の解消を目的に、令和6年4月1日から相続等により不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化され、違反者は10万円以下の過料の対象となりました。同様の目的で、令和8年4月1日からは、登記名義人の氏名(名称)や住所の変更日から2年以内に変更登記の申請を行うことが義務化されます。違反者は、5万円以下の過料の対象です。
個人の場合、氏名の変更は「結婚・離婚」や「養子縁組・離縁」によるものがほとんどですから頻繁に起きることはないと考えられますが、住所の変更は人によってはそれなりにあり得ます。また、相続登記は不動産を相続等で新たに取得した時のことなので登記についても頭に浮かびやすいのに対し、変更登記は不動産の取得時のことではないため登記にまで考えが及ぶかどうかは微妙です。それにも関わらず、変更日から2年以内の変更登記申請が義務化され、違反すれば過料の対象ということですから、ある意味、相続登記よりも負担が大きくなる可能性があります。
そこで、登記名義人の負担軽減のため、変更登記の申請の義務化と同時に、登記官が職権で変更登記を行う仕組みも令和8年4月1日からスタートします。具体的には、登記官が住基ネット情報を定期的に検索して登記名義人の氏名・住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることについて本人の意思確認を行い、本人の了解が得られた場合に限り職権で変更登記をするという流れになります。本人の了解を必要としているのは、DV被害者のように最新の住所を公示することに支障がある者もいること等を踏まえたものです。また、登記名義人が自分で変更登記を申請する場合、土地は1筆、建物は1棟あたり1,000円の登録免許税負担が発生しますが、職権での変更登記の場合は本人の費用負担はありません。
ただし、登記官が登記名義人の住基ネット情報を検索するためには、本人から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を事前に申し出てもらう必要があります。
そこで、職権で変更登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の「検索用情報」を併せて申し出る(申請書に記載する)ことになります。
また、令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者として登記簿に記録されている者も、同日以降、「検索用情報」を自主的に申し出ることができます。
制度の概要は、以下のとおりです。
【①新たに不動産を取得して登記申請する場合】
1 同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
令和7年4月21日以降、所有権の保存登記や移転登記等の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります。
2 検索用情報の具体的な内容
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
メールアドレスは、登記官が職権で変更登記を行おうとする時にその可否を登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。そのため、代理人による申請の場合であっても、登記名義人本人のメールアドレスが必要となります。
なお、手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスにも振り仮名の記載が必要とされています(例えば、「0」が数字の「ゼロ」なのかアルファベットの「オー」なのかを正しく判別するため)。メールアドレスを持たない場合には、無い旨を申請情報の内容として記載します。その場合、登記官が職権による変更登記を行うことの可否を確認する際には、メールに替えて登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。
3 その他
(1) 職権による変更登記の対象となる不動産
令和7年4月21日以降、登記申請と同時にする検索用情報の申出がされた場合、職権による変更登記の対象となるものは当該不動産に限られます。それ以前に所有者として登記済みの不動産については、別途検索用情報を提供しなければ職権による変更登記の対象とはなりません(下記②参照)。
(2) 検索用情報の申出に関する添付情報
登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名及び生年月日を証する情報を提供することとされています。もっとも、従来から登記申請時には住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって前記情報を兼ねることができることから、追加で必要となる添付情報は生じない予定です。
【②令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出】
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者は、別途、検索用情報の申出を自発的にすることができます。この申出は、令和7年4月21日以降、オンライン上で行うか、申出書を登記所に提出する方法により行うことになります。なお、登録免許税等の費用は掛かりません。
ここまでは、登記名義人が自然人(個人)の場合についてのものでした。
なお、登記名義人が法人の場合も、令和8年4月1日から名称や住所の変更登記の申請が義務化され、違反すると5万円以下の過料の対象です。それと同時に、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で変更登記をすることができる仕組みもスタートします(当該法人の承諾不要)。それを可能にするために、令和6年4月1日以降に法人が新たに所有権の登記をする場合には、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項(以下「法人識別事項」といいます。)が登記事項に追加されました。あわせて、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人についても、当該法人からの自発的申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができるようになっています。
個人の場合は「検索用情報」、法人の場合は「法人識別事項」の提出を済ませておけば、将来、登記名義人による変更登記が未了であっても、最終的には登記官が職権で変更登記を行うことが可能となります。それにより、登記名義人の負担は軽減され、変更登記の義務違反に問われることもなくなります。非常に便利な制度ですから、ぜひよく理解しておきたいところです。